
平成特集|ストレス社会の健康法 平成で話題になったストレス解消法
現代は「ストレス社会」といわれ、平成に入ってからこれまで、新たなリラックス方法が生まれては、話題になりました。ストレスはさまざまな病気の遠因であり、ストレス対処法は多くの方の関心事です。そこで今回は、平成を振り返って話題になったり、見直されたりしたストレス解消法をご紹介します。
現代は「ストレス社会」といわれ、平成に入ってからこれまで、新たなリラックス方法が生まれては、話題になりました。ストレスはさまざまな病気の遠因であり、ストレス対処法は多くの方の関心事です。そこで今回は、平成を振り返って話題になったり、見直されたりしたストレス解消法をご紹介します。

誰もが手軽に始められる 「コーピングリスト」
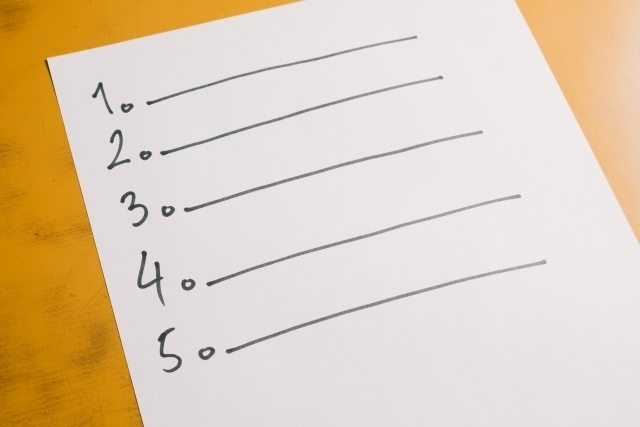
「コーピング」とは、おおまかにいえば「対処」のことで、「ストレスコーピング」はストレスに対処する技術や能力をいいます。ストレスコーピングはいくつもの方法がありますが、中でも自分の心が軽くなる手段を書き出す「コーピングリスト」がおすすめです。
コーピングリストは、まず、自分が「これをしていると気持ちが和らぐ、前向きになれる」ということを書き出してみます。例えば「○○のご飯を食べに行く」「とっておきの入浴剤で長風呂をする」「猫をなでる」など、できるだけ細かく具体的で、実現可能なものにしましょう。リストの目標は100個。あまりお金をかけず、自分ひとりでできるものにするのがポイントです。
そして、ストレスを感じた時に、コーピングリストから気分に合うものを選んで実践をします。効果を確かめて足したり削ったりして、自分にぴったりの気晴らしリストを作りましょう。落ち込んで何も考えられない……そんな時でもコーピングリストがあれば、自分の気分に合ったものをリストから選んで、ストレスに対処できるのです。
腸内環境を整える 「腸活」

近年の研究で、心と腸は、お互いの健康に深く関わっていることが分かってきています。心がストレスを受けると、便秘や下痢になりやすいというのは、経験したことがある方も多いのではないでしょうか。また、腸の調子が悪いと、体調や気分に悪影響を及ぼします。
「腸活」とは、「腸の働きを改善して、おなかのなかから健康になろう」という考え方。免疫機能が集中する腸を改善することで、病気になりにくくストレスの影響を受けにくい心身を作ることを目指します。乳酸菌や発酵食品、食物繊維を積極的に摂って、腸がよろこぶ食生活を送りましょう。
腸と乳酸菌の関係については、こちらの記事も参考になります。
女性を中心に静かなブーム 「お灸」

温熱刺激を与えることで、免疫作用をアップさせることが認められているお灸。冷えやむくみを軽減するツボもあることから、女性を中心にひそかなブームが続いています。ツボの数はWHO(世界保健機関)が認定しているものだけでも365カ所もあり、なかにはやる気がおきない・イライラするなど、心の不調を軽減するツボもあるのです。
また、お灸の原料であるもぐさの精油には、消毒・殺菌・鎮静・鎮痛作用などがあり、香りにはリラックス効果があることが分かっています。ご家庭で手軽にできるセルフケアのひとつとして、お灸を試してみるのもおすすめです。
はじめての方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
気持ちよく歌ってストレス発散 「カラオケ」

カラオケボックスのブームが本格化したのは、昭和最後の年である昭和63年ごろ。平成に入ってからは、カラオケといえば「個室型」を指すことが一般的になりました。知っている人だけで思う存分歌える気軽さで、カラオケボックスは今でも人気の娯楽のひとつです。
カラオケの運動としての効果や、ストレス発散効果が研究されはじめたのは、平成の始めごろ。平成10年あたりからは、カラオケを医療や福祉に活用する動きも見られています。天気に左右されないうえ、手ぶらで来店できるカラオケは、手軽なストレス発散方法のひとつといえるでしょう。
ストレスの主な原因となる対人関係や仕事の問題は、環境を変えてしまえば解消するかもしれませんが、なかなか難しいのが現状です。だからこそ、ストレスに過剰に反応したり、気づかないふりをしたりするのではなく、ストレスとうまく付き合う技術が求められているのでしょう。マイナスな気持ちになってしまったら、ここでご紹介したストレス解消法を思い出して、ぜひ実行してみてください。
関連する投稿
健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?
人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。
秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。
「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。
最新の投稿
健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?
人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。
朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。
コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。
春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。



















































