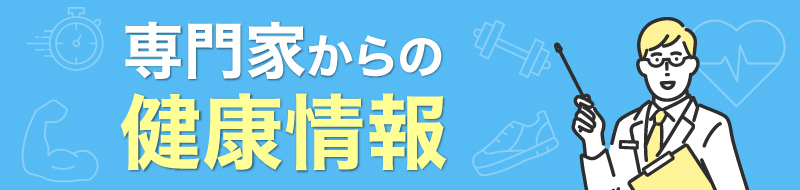おいしく健康をサポート お酢のチカラ
お酢は、昔から日本人の食に欠かせない調味料。
料理の味を引き立てるだけでなく、健康に良い調味料として改めて注目されています。
お酢の種類や健康効果を知り、食卓に賢く取り入れましょう。
教えていただいたのは

監修:石原 新菜(いしはら にいな)さん
医師:イシハラクリニック副院長
帝京大学医学部卒業。学生の頃から世界各国の病院を視察して自然医学を学び、帝京大学附属病院での研修医を経て、父・石原結實氏のクリニックで主に漢方医学、自然療法、食事療法を用いた病気治療にあたる。講演、テレビへの出演も多く、『おいしくて体に効くお酢レシピ』(監修・扶桑社)など著書も多数。
お酢の〝すっぱさ〟が健康に貢献する
紀元前5000年頃のバビロニア( 現在のイラク南部)ですでにつくられていたお酢は、昔から体によいものとされ、古代ギリシャや中国では薬のようにも使われていたそうです。
食酢(しょくず)は醸造酢(じょうぞうす)と合成酢(ごうせいす)に大別されますが、日本の家庭では主に醸造酢が使われています。醸造酢はまず、穀物や果実に酵母を加えてアルコール発酵させます。そこに酢酸菌を加えてさらに発酵させた後、一定の熟成期間が設けられます。
こうして完成したお酢にはアミノ酸や糖類など様々な栄養素が含まれていて、そのうち最も多い成分が酢酸(さくさん)です。この酢酸こそが酸味のもとになるものであり健康をサポートしてくれるのです。
お酢に期待できる健康効果とは?
酢の主要成分である酢酸が手助けする主な健康効果をご紹介。
1.食欲を増進させる
お酢のさわやかな酸味や香りが嗅覚と味覚を刺激し、唾液や消化液の分泌を高めて食欲を増進させます。唾液には細菌や異物を防ぐ働きがあるので免疫力アップにもつながります。

2.疲労を回復させる
疲労の回復にはグリコーゲン(糖の一種)の摂取が重要ですが、お酢と糖分を一緒にとることで酢の成分の酢酸がグリコーゲンの合成を助けます。また、酢酸は体内でクエン酸に変換され、疲労のもとである乳酸を減らしてくれます。

3.食当たりを予防
酢酸には食べ物を傷みにくくする防腐効果があります。ピクルスなどの酢漬けや酢で〆た魚が昔から食べられてきたのも、お酢の保存力を生かした先人の知恵といえます。

4.減塩をサポート
酸味には塩味や食材の味を引き立てる効果があります。また、お酢を料理に使うとコクが出るため、塩分を少なくしても物足りなさを感じさせず、塩分の摂り過ぎを軽減してくれます。

毎日大さじ1杯で健康に!
お酢は毎日大さじ1杯(約15ml)ほどとるとよいでしょう。数回に分けたほうが効果が持続するのでおすすめです。お酢を飲む場合は、そのまま飲むと喉や胃を痛める恐れがあるので5~8倍に薄めて飲むとよいでしょう。
お酢の種類を知ろう!
お酢には原材料やつくり方によって様々な種類があり、味わいも異なります。
ここでは日本の家庭でよく使われている主な醸造酢の種類をご紹介。
特徴や料理との相性を知って上手に使い分けましょう。

【穀物酢】
小麦、大麦、コーンなどの穀類のうち1種類または2種類以上を、1Lにつき合計40g以上使用して醸造した酢。
特徴
すっきりとしてさわやか
クセがなく幅広く活躍する万能酢。豚肉や鶏肉を煮るとさっぱりとした口当たりに。

【米酢】
穀物酢の一種で、米の使用量が1Lにつき40g以上のもの。米酢のなかでも米だけを使用したものを純米酢という。
特徴
甘みがあってまろやかな味わい
寿司、酢の物などの和食に合う。

【黒酢】
穀物酢の一種で、発酵および熟成によって褐色または黒褐色になったもの。主に1Lにつき180g以上の大麦のみを利用した大麦黒酢と、1Lにつき180g以上の米に小麦や大麦を加えた米黒酢がある。
特徴
うまみ成分が豊富でやわらか
料理にコクを与え、中華料理と相性がよい。また、水や炭酸水で割って飲むのもおすすめ。

【果実酢】
リンゴやブドウなどの果実1種類または2種類を1Lにつき合計300g以上使用したもの。ワインビネガーやバルサミコ酢も果実酢の一種。
特徴
フルーティーな香りと酸味
サラダのドレッシング、水や炭酸で割ったドリンクに。また、ヨーグルトやアイスのトッピングにも活躍。
お酢の正しい保存法をチェック!
ふだん、お酢をどのように保存していますか?
お酢は強い殺菌力を持つため、米酢などの穀物酢は腐ることはありません。酸化を防ぐために開封後は直射日光や高温を避け、台所の下などの冷暗所で保存しましょう。一方、果実酢のような果汁や糖分を加えている酢は次第に腐ってしまうので開封後の保存は冷蔵庫で。穀物酢は賞味期限が過ぎてしまっても窓や畳の掃除に活用できます。

漬けるだけ!簡単お酢レシピ
お酢は身近な食材と組み合わせることで、より美味しく、効果的にとることができます。切って漬けるだけで、健康によく、常備菜にもなる簡単レシピをご紹介!
酢タマネギ(要冷蔵:1ヵ月)

タマネギには血流を促進する効果があります。同様の効果があるお酢との組み合わせで、血行改善が期待できます。
●おすすめの食べ方
和洋中どの料理とも相性抜群。そのままサラダや和え物に加えたり、みじん切りにすれば調味料としても活躍。
材料(分量は目安)
- タマネギ…1個
- 塩…小さじ1/2
- 米酢または穀物酢、黒酢…適量
- ハチミツ…お好みで
作り方
- タマネギの皮をむき、薄切りにする
- タマネギをボウルに入れて塩をふり、30分以上置いて辛みを抑える
- 保存容器にタマネギを入れて完全に浸るまで※お酢を加える
- ハチミツを加えて混ぜる。1週間ほど漬け込むとまろやかに
※酢に完全に浸っていないと腐りやすくなります。
酢ショウガ(要冷蔵:2週間)

ショウガは冷えの改善に効果的。血流をよくするお酢と一緒に とることで代謝アップにつながります。
●おすすめの食べ方
炒め物や煮物の風味付けに活躍するほか、タレの調味料、麺類の薬味にも。黒酢ならコクが出て中華料理や肉料理にもマッチ。
材料(分量は目安)
- ショウガ…200g
- 米酢または穀物酢、黒酢…適量
- ハチミツ…お好みで
作り方
- ショウガを洗い、水気を取る。汚れは包丁でそぎ落とす
- 皮付きのまま、薄切りかみじん切りにする
- 保存容器にショウガを入れて完全に浸るまで※お酢を加える
- ハチミツを加えて混ぜる。すぐに食べられるが、ひと晩置いたほうがまろやかに
※酢に完全に浸っていないと腐りやすくなります。
レモン酢(要冷蔵:1ヵ月)

お酢はレモンのビタミンCが壊れるのを防ぐ効果があります。ま た、疲労回復に効果的な成分が両方に含まれています。
●おすすめの食べ方
レモンはそのままでも炒め物や煮物の具にも。漬け酢はサラダのドレッシングな どに。水や炭酸で割るとさわやかなドリンクに。
材料(分量は目安)
- レモン…2個
- 米酢または穀物酢、黒酢…2カップ
- ハチミツ…大さじ3
作り方
- レモンをしっかり洗い、水気を取る
- ヘタを取り、5mm幅の輪切りにする
- 保存容器にレモンを入れて完全に浸るまで※お酢を加える
- ハチミツを加えて混ぜ、1週間置く
※酢に完全に浸っていないと腐りやすくなります。
お酢が苦手な方は
ハチミツを加えるとよいでしょう。また、お酢は加熱すると酸味が和らいで食べやすくなります。お酢の栄養成分は加熱しても壊れません。
関連する投稿
コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。
肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。
普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。
「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。
冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。
最新の投稿
朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。
コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。
春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。