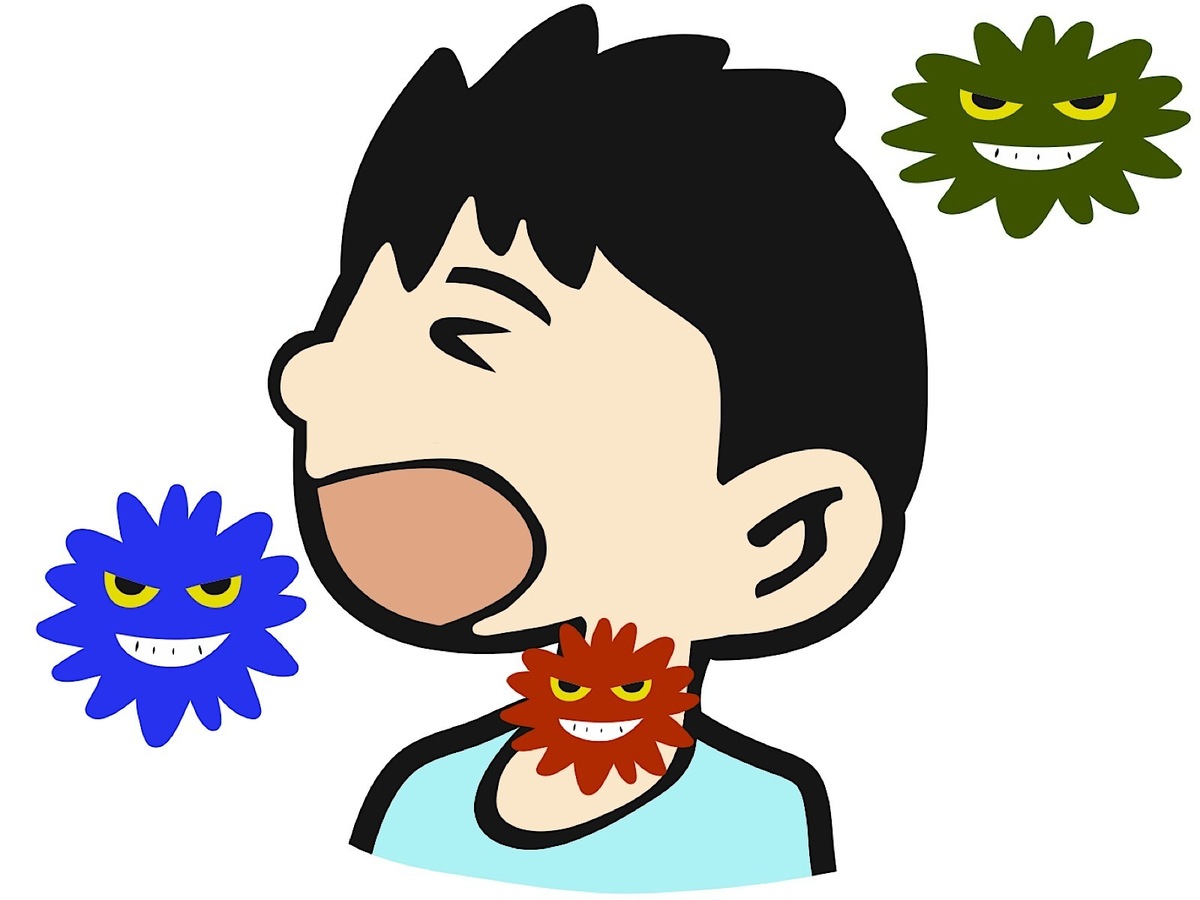健康習慣|体調不良の原因は「隠れ酸欠」? マスク生活で気をつけたい習慣とは
新型コロナウイルス感染症の流行により、季節にかかわらず外出時は常にマスクを着用することはもはや日常となりました。従来のように一時的なマスクの着用であれば問題はなかったのですが、着用時間が増えていることが原因で体調不良が起こる可能性があります。そこで今回は、マスク着用によって起きる「隠れ酸欠」についてご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の流行により、季節にかかわらず外出時は常にマスクを着用することはもはや日常となりました。従来のように一時的なマスクの着用であれば問題はなかったのですが、着用時間が増えていることが原因で体調不良が起こる可能性があります。そこで今回は、マスク着用によって起きる「隠れ酸欠」についてご紹介します。

こんな不調を感じていませんか? 「隠れ酸欠」の症状例
マスクを日常的に着用し始めてから、体調がいまいち優れないと感じたことはありませんか?疲れが取れにくかったり、集中力が続かなかったりする、または体が重くだるく感じる、マスクをしているのに風邪をひきやすくなった……などの症状に、思い当たるふしがあるという方もいるでしょう。もし以下のような症状がある場合、「隠れ酸欠」が原因の可能性があります。
- 頭痛・めまい
- 腰痛・肩こり
- 疲れやだるさが続く
- 集中力が続かない
- 風邪をひきやすくなった
これらの不調が必ずしも隠れ酸欠が原因とは断定できないものの、長時間のマスク着用をはじめてから起こっているのであれば、マスクによる「隠れ酸欠」を疑ってみましょう。
マスクで酸欠になってしまう原因とは

マスクを長時間着用していると、鼻と口を覆った状態が長く続きます。すると呼吸が浅くなってしまい、吸い込める酸素の量が減ってしまうことが、酸欠になる原因です。さらに、マスクをしていると口呼吸をしてしまいがちです。口呼吸のほうが取り込める酸素量が多いと思われがちですが、実は鼻から吸ったほうが肺の奥まで酸素が行き届きやすいのです。つまり、マスクをしているときの口呼吸だけでは、体に十分な酸素を取り込めず、あまり自覚がないまま酸欠状態になっていることがあるのです。
鼻呼吸と口呼吸については、以下の記事も参考にしてみてください。
普段の生活でも隠れ酸欠に? 注意したい習慣とは

隠れ酸欠の原因は、マスクだけではありません。普段の生活のなかにも、実は隠れ酸欠になりやすい習慣があるのです。たとえば、日ごろストレスを感じることが多いと、呼吸を浅くしてしまう交感神経が優位になります。さらに、ストレスから身を守るために無意識のうちに背中を丸めてしまいがちです。ストレスにより交感神経が優位になること、そして背中を丸める姿勢は酸素を取り込みにくくなることが、隠れ酸欠を引き起こしてしまうのです。
コロナ禍で、お家時間が増えたり、出勤せずに自宅で仕事をしたりする人も増えています。自宅で、つい猫背の姿勢で長時間の作業や仕事をしてしまうことはありませんか?より多くの空気を取り込むには横隔膜を動かす必要がありますが、猫背は肺やおなかを圧迫し、気道を狭くする姿勢なので横隔膜を十分に動かせません。そのため、猫背が原因で取り込める空気の量が減り、隠れ酸欠になることも考えられます。
隠れ酸欠を予防するための方法と対策

さまざまな体の不調を引き起こす隠れ酸欠を防ぐには、一時的にマスクを外してみましょう。「3密」の場所を避けて人との距離を取った上で、腹式呼吸を行います。胸とおなかに手をおき、鼻から息を吸い込むと、おなかが膨らむのが分かるはずです。その状態でゆっくりと口から息を吐き出しましょう。
猫背をなおして背筋を伸ばし、鼻呼吸を意識するだけでも、取り込める酸素量を増やせます。「背筋を伸ばして鼻からゆっくりと息を吸って、口から息を吐く」を30分につき10回程度実践すると、隠れ酸欠改善が期待できます。
マスク生活だけではなく、日常生活にも原因が潜んでいる「隠れ酸欠」。体調不良が続くという場合は、普段の習慣や姿勢を見直すだけで改善するかもしれません、ぜひ、今回紹介した正しい姿勢や呼吸方法を実践してみてください。
関連する投稿
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。
秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。
「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。
パソコンやスマホによる目の疲れや、涙の量が減少するドライアイ、慢性的な目の疲れによる眼精疲労など、増加する目のトラブルは現代病のひとつ。目の疲れが続くと、肩こりや頭痛などの症状も出てしまうので厄介です。今回はご自身でできる、目のセルフケアをご紹介します。
最新の投稿
朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。
コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。
春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。