
健康法|今から取り組む「フレイル」予防
「フレイル」とは、介護が必要になる手前の虚弱な状態を示す概念。昨今のコロナ禍で外出する機会が減ったことにより、フレイルに陥る高齢者が増加していると指摘されています。今回は、健康なうちから取り組みたいフレイル対策についてご紹介。フレイルの兆候を知ることができる簡単なチェック項目もありますので、自分にあてはまるものがないか確認してみてください。

「フレイル」とは、介護が必要になる手前の虚弱な状態を示す概念。昨今のコロナ禍で外出する機会が減ったことにより、フレイルに陥る高齢者が増加していると指摘されています。今回は、健康なうちから取り組みたいフレイル対策についてご紹介。フレイルの兆候を知ることができる簡単なチェック項目もありますので、自分にあてはまるものがないか確認してみてください。
「フレイル」とは?
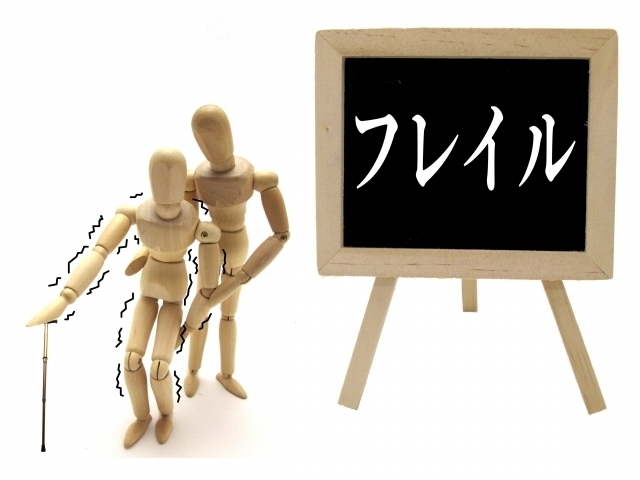
フレイルとは、日本老年医学会が2014年に提唱した概念で、英語で“虚弱”を意味する「Frailty(フレイルティー)」がその由来です。フレイルは、健康な状態と介護が必要な状態の中間に位置し、加齢によって心身の働きが衰え、社会的なつながりが弱くなっている状態のことをいいます。多くの高齢者は、フレイルを経て要介護状態へ進むと考えられています。
フレイルには統一された評価基準はありませんが、国立長寿医療研究センターが2020年に改定した日本語版フレイル基準(J-CHS基準)がよく用いられます。次の5つの項目のうち、3つ以上があてはまるとフレイルの可能性が高く、1~2つがあてはまる場合は“プレフレイル”(フレイルの前段階)だといわれています。
1.体重減少
6ヵ月で、意図しない体重減少が2キロ以上ある
2.筋力低下
利き手の握力が、男性で28キロ未満、女性で18キロ未満
3.疲労感
ここ2週間で、わけもなく疲れたような感じがする
4.歩行速度
通常歩行速度が、1秒間に1.0メートル未満
5.身体活動
「軽い運動・体操をしているか」「定期的に運動・スポーツをしているか」のいずれの問いにも「週に1回もしていない」と回答
フレイルを防ぐポイント

フレイルは、自分の状態を知り適切に対処することで、進行を遅らせることができるといわれています。また、フレイルの状態になったとしても、日々の心がけによって、再び健康な状態に戻る可能性も期待できます。具体的にはどのような取り組みをしたらよいのか、詳しく見ていきましょう。
■たんぱく質をたっぷり摂る
バランスのよい食事を3食しっかりと食べることはもちろんですが、特にたんぱく質を意識して摂ることがポイント。たんぱく質が不足すると筋肉が衰えやすく、フレイルに陥りやすいといわれています。日本サルコペニア・フレイル学会が発表したガイドラインによると、筋肉量を維持するためには体重1キロあたり1グラム以上のたんぱく質を摂取するのがよいそうです。
■口周りの筋力を鍛える
咀嚼や発音などの口腔機能は、「食べる」「話す」といった動作をするために欠かせません。噛む力や飲み込む力が衰えると食生活に支障をきたし、滑舌が悪くなると会話を楽しめなくなります。口周りの健康を保つために、しっかり噛んで食べるとともに、舌を動かすトレーニングを行いましょう。
■1人ではなく、家族みんなで食事を
人や社会とのつながりが希薄になると、認知機能が低下し、フレイルに陥るきっかけになりやすいことが分かっています。食事の時は家族団らんを心がけたいもの。また、電話やオンラインツールを活用してコミュニケーションをとるのもよいですね。
■体操や散歩など軽い運動をする
昨今、おうち時間が増えた影響で、外出の機会が減っている方が多いかもしれません。しかし、家に閉じこもってばかりで体を動かさない状態が続くと、心身の機能が低下してしまいます。庭先で簡単な体操をしたり、人混みを避けて散歩をしたりするのがおすすめです。感染症対策をとりながら、無理のない範囲で続けましょう。
健康なうちから取り組みを

フレイルは心身のささいな衰えからはじまります。しかし、そのまま放っておくと、ドミノ倒しのようにどんどん進行してしまいます。この状態は“フレイル・ドミノ”といわれています。そうならないためには、フレイルの兆候を早期に発見することが大切。すでに症状があらわれている場合は、それ以上進行しないよう、すぐに対策や治療を行いましょう。
日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超えています。一方で、元気に自立して日常生活を送れる健康寿命は70歳代前半と、平均寿命と約10年の差があります。つまり、その間は介護が必要な状態になりかねないということです。フレイルの予防は、健康寿命を延ばすためにとても重要です。フレイルについて正しい知識をもち、毎日の食事や運動を意識して心身の健康の維持に努めましょう。自分はもちろん周りの家族にも目を配ってみてくださいね。
関連する投稿
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。
秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。
「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。
パソコンやスマホによる目の疲れや、涙の量が減少するドライアイ、慢性的な目の疲れによる眼精疲労など、増加する目のトラブルは現代病のひとつ。目の疲れが続くと、肩こりや頭痛などの症状も出てしまうので厄介です。今回はご自身でできる、目のセルフケアをご紹介します。
最新の投稿
朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。
コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。
春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。
















































