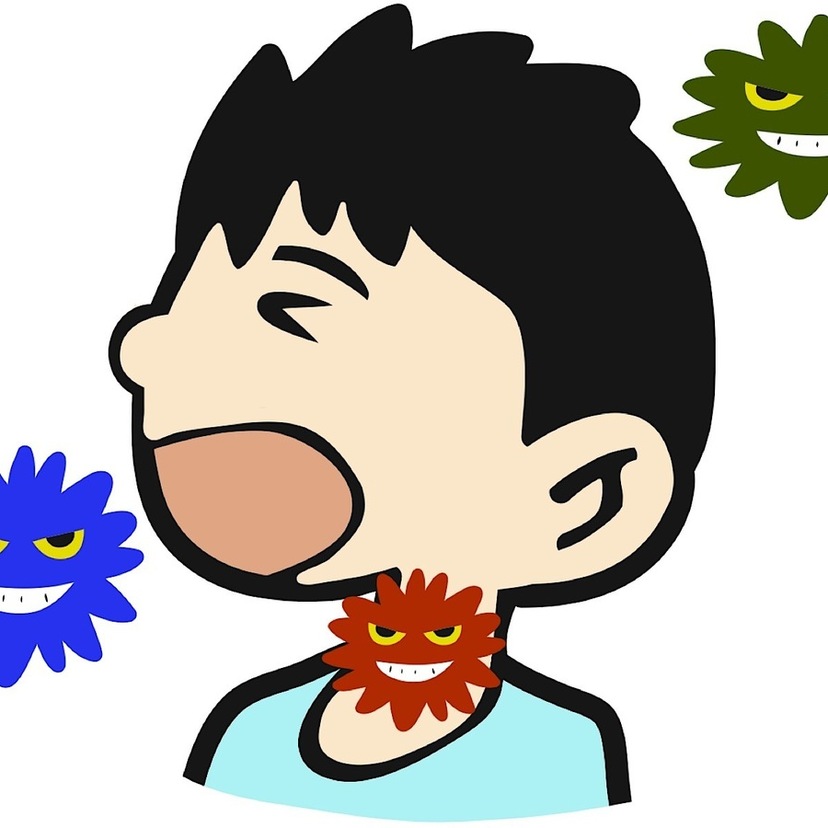
健康習慣|その不調、口呼吸が原因かも? 鼻呼吸の大切さを知っておこう
本来、人は鼻で呼吸をするようにできています。しかし、口で呼吸をしていることも意外と多いもので、なかには口で呼吸するほうが楽という方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、意外と知られていない鼻の優秀な機能と、その効果についてご紹介します。鼻呼吸の習慣がつくコツもお伝えしますので、日々の健康習慣にぜひ加えてみてください。
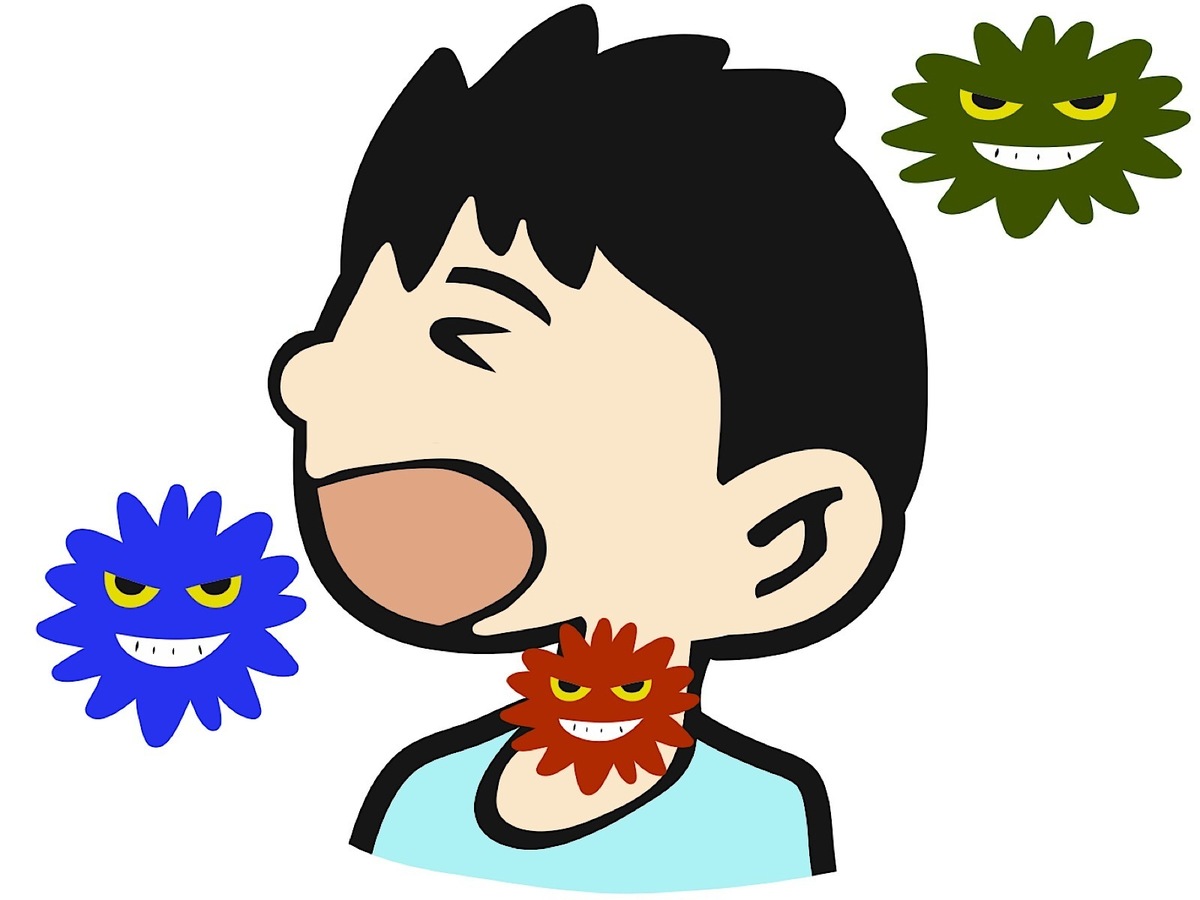
本来、人は鼻で呼吸をするようにできています。しかし、口で呼吸をしていることも意外と多いもので、なかには口で呼吸するほうが楽という方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、意外と知られていない鼻の優秀な機能と、その効果についてご紹介します。鼻呼吸の習慣がつくコツもお伝えしますので、日々の健康習慣にぜひ加えてみてください。
「口」と「鼻」では大違い、鼻の役割をあらためて
みなさんは普段、鼻と口のどちらで呼吸をしているでしょうか。息を吸って吐くだけならば、どちらでも可能ですよね。例えば風邪や花粉症で鼻が詰まった時には、鼻の代わりに口で呼吸をするでしょう。口は鼻より大きく開けられるので、よりたくさんの空気を取り込めます。しかし、いつも口呼吸でいいのかというと、そんなことは全くありません。
鼻には口にはない、呼吸のための機能が備わっています。そこで、鼻呼吸の大きな3つの働きをご紹介します。
■加湿器
鼻から吸った空気は、鼻腺からの分泌液で加湿されます。その威力は想像以上で、湿度は約70~90パーセントまで高まります。
■空気をキレイにする
空気中のチリやホコリは鼻毛が、細菌やウイルスは鼻の粘膜がキャッチして、体内への侵入を防いでくれます。さながら空気清浄機のような役割です。
■空気をあたためる
鼻呼吸は、口呼吸と比較して2℃ほど加温能力が高いことがわかっています。あたためられて潤った空気が肺に運ばれることで、肺の伸縮性や換気能力が正常に保たれます。
口呼吸のリスク
「潤い・清く・あたたかい」空気が鼻呼吸で運ばれる空気だとすれば、口呼吸はその反対で「乾燥して・汚れた・冷たい」空気を運んでいます。
また、口呼吸は口内を乾燥させるため、唾液が持つ殺菌・消毒作用がきちんと働きません。口内が乾くことによって、細菌が繁殖しやすい環境となり、口臭・歯周病・ドライマウスなど、口内トラブルのリスクが高まります。さらに、口呼吸は前頭葉を疲れさせるため、注意力や作業効率の低下を招くこともわかっています。
鼻呼吸を習慣づけるには
鼻呼吸のメリット、それから口呼吸のリスクについて説明してきました。では、うっかり口呼吸にならないために、どんなことができるでしょうか。
まず、みなさんの舌は、普段どこにありますか?そのときどきで違うという方は、口呼吸になりやすいタイプです。また、特定の歯に常に当てているという場合は、歯並びが悪くなることもあるので注意が必要です。
舌は、上顎のくぼみにすっぽり収まっているのが正しい状態です。舌先は「ら」を発声した時の位置に当てて、舌の中央は上顎のくぼみに入るようにと意識するとよいでしょう。舌を正しい位置に置くと、舌が邪魔して空気が通らないため、自然と鼻呼吸になります。慣れるまでは意識的に位置確認を行うようにしてみてください。舌の位置を維持する筋肉がつけば、顔のたるみ予防にもなります。
鼻詰まりがある方は、まずはその改善を

花粉症や鼻炎など、鼻が詰まることが多い方は、どうしても口呼吸になってしまいます。まずはこれらの鼻詰まりの原因を治していくことが先決です。鼻詰まりの改善は、その原因に合わせて適切な対応をしましょう。花粉症の治療をする、鼻うがいで鼻を通す、いびきが癖になっている場合には口いびき外来もあります。鼻詰まりが改善されるまでは、部屋に加湿器を置いたり、マスクをしたりなど、乾燥した冷たい空気を吸わない環境作りをしてみてください。
鼻は呼吸に最適であるように作られていることが、おわかりいただけましたか?鼻呼吸を意識することで、インフルエンザ・風邪対策や、口内トラブルの軽減に役立ちます。鼻呼吸と口呼吸はちょっとの違いのようで、結果は大きく異なってきます。まずは今日、舌の位置を意識するところからはじめてみてください。
関連する投稿
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。
秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。
「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。
パソコンやスマホによる目の疲れや、涙の量が減少するドライアイ、慢性的な目の疲れによる眼精疲労など、増加する目のトラブルは現代病のひとつ。目の疲れが続くと、肩こりや頭痛などの症状も出てしまうので厄介です。今回はご自身でできる、目のセルフケアをご紹介します。
最新の投稿
朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。
コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。
春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。
















































