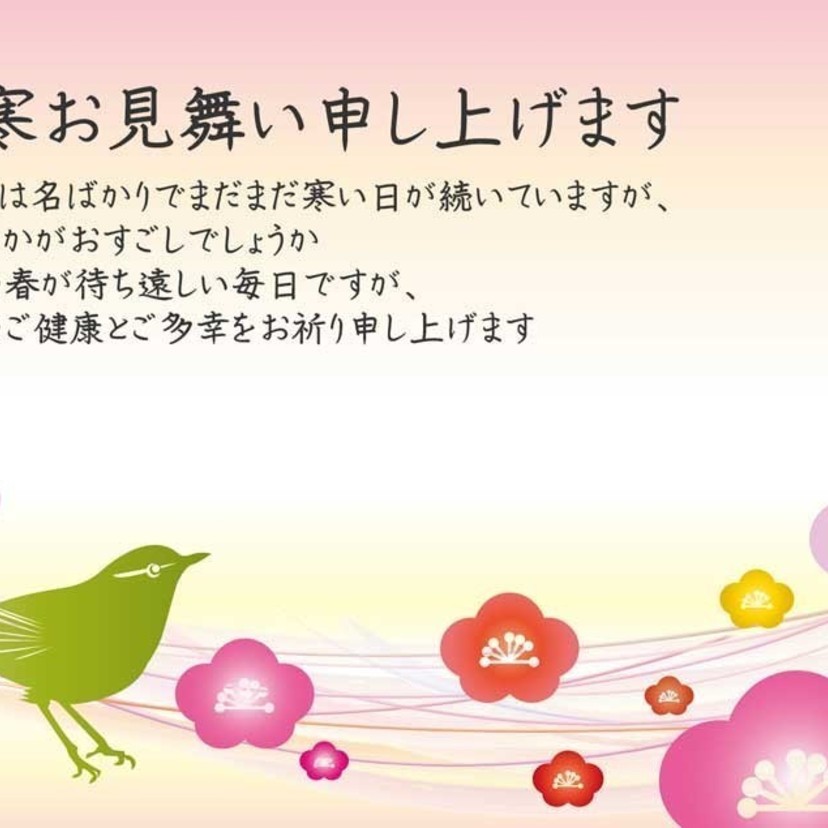
イベント事のマナー|余寒見舞いの役割 書き方と文例
余寒見舞いは、年賀状を送りそびれたり、年明けに忙しくしているうちに、気がつけば寒中見舞いも間に合わない……といった時にお送りしたい季節のごあいさつです。「寒中見舞い」は聞いたことがあるが、「余寒見舞い」は知らなかったという方もいらっしゃるかと思います。今回は、寒中見舞いと余寒見舞いの違いや、出す時期、書き方などをご紹介します。
余寒見舞いは、年賀状を送りそびれたり、年明けに忙しくしているうちに、気がつけば寒中見舞いも間に合わない……といった時にお送りしたい季節のごあいさつです。今回は、余寒見舞いを出す時期や、書き方をご紹介します。
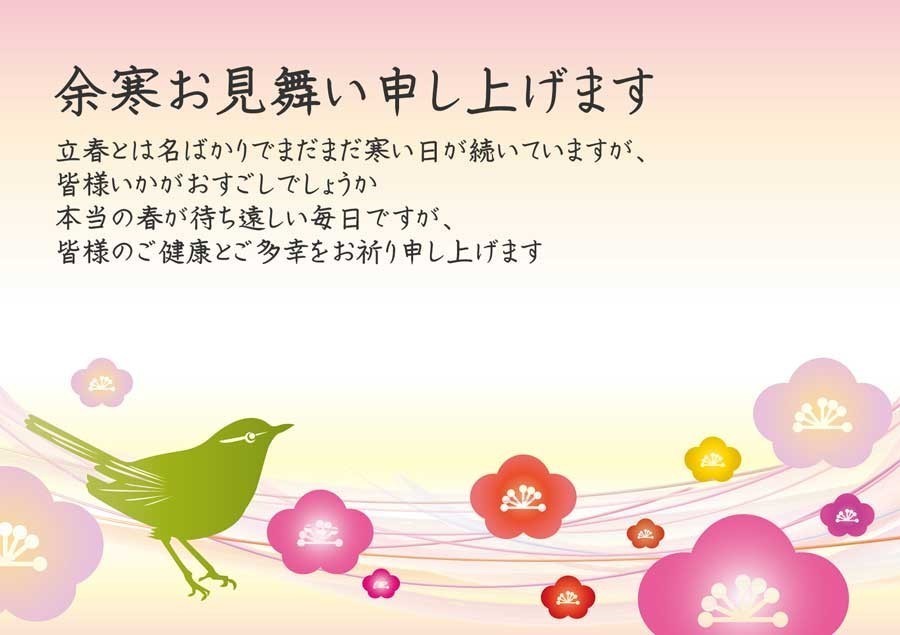
余寒見舞いの役割
余寒見舞いは「寒さの残る時期に送るあいさつ状」のことで、主に以下のような役割をします。
・季節のあいさつ、近況の報告
・相手から年賀状や寒中見舞いをいただいたが、返事が遅れた時の返礼
・喪中などで年賀状を送れなかった場合の、年始のあいさつとして
・こちらを喪中と知らず、年賀状をくださった相手に喪中の報告とおわび
“寒中見舞い”と“余寒見舞い”の違い
寒中見舞いも余寒見舞いも、どちらも寒い時期に相手を気遣い、近況をお知らせするという目的は同じですが、出す時期が異なります。
寒中見舞いは松の内が明けてから立春までの、最も寒い時期に送ります。松の内は関東地方では1月7日、関西地方では1月15日の地域が多く、10日や15日までを松の内とする地域もあります。
余寒見舞いは立春以降、寒さが続く2月下旬ごろまでに送ります。立春を過ぎると暦の上では春となりますが、「春とはいえまだ寒いですね」という意味で「余寒」を使います。
寒中見舞いは暑中見舞いと同じく最も厳しい気候の時期に送るもの、余寒見舞いは残暑見舞いのように厳しい気候を超えたあとに送るもの、と捉えると覚えやすいでしょう。
文例で見る、余寒見舞いの書き方
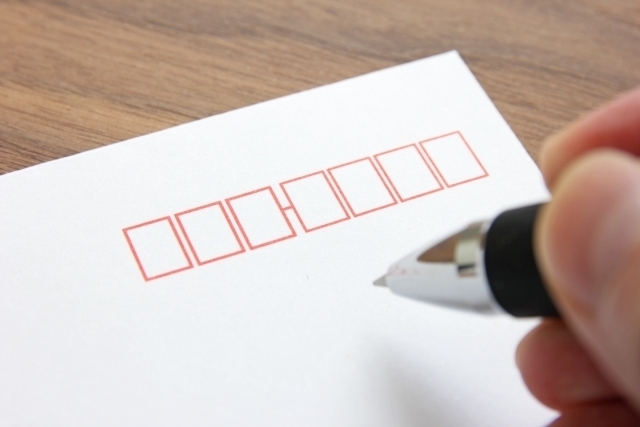
余寒見舞いの書き方にきっちりとした決まりはありませんが、以下のような順序で書くと整ったあいさつ状になります。先方が親しいご友人やご親戚なら、文例よりも、親しみを込めた文体で書いても構いません。
1. ごあいさつの言葉
「余寒お見舞い申し上げます」「暦の上では春とはいえ…」などで始めます。「余寒見舞い」という言葉は必須ではなく、寒さが残ることを書くことで余寒見舞いとなります。
2. 先方の様子をうかがう / 自分の近況を伝える / 年賀状や寒中見舞いをいただいたお礼や、返事が遅くなったことへのおわび
3. 先方の無事を祈る / 今後のお付き合いを願う
4. 日付(○○年○月)
文例1:年賀状などをいただいた方へ
余寒お見舞い申し上げます。
先日は年始のごあいさつをいただきまして、ありがとうございました。
私どももおかげさまで、つつがなく過ごしております。
季節の変わり目、お風邪など召されませぬようご自愛くださいませ。
○○○○年(または元号)○月
文例2:通常の余寒見舞い
寒が明けてもなおも寒さの残る折、○○様にはお障りございませんか。
おかげさまで私どもも、皆元気にしております。
まだしばらくは厳しい寒さが続きそうとのこと、春の訪れが待ち遠しいですね。
時節柄、どうぞお体を大切にお過ごしください。
○○○○年(または元号)○月
電話やメールは便利ですが、お便りが届くとやはりうれしいもの。先方の健康と親しいお付き合いを願って書いたごあいさつは、きっと気持ちが伝わります。親しい方はもちろん、しばらく交流のなかった方へも、今年は余寒見舞いを出してみてはいかがでしょうか。
関連する投稿
ゴールデンウィークから初夏にかけては、陽気に誘われて過ごしやすい時季です。そこで今回は、これまでご紹介してきた旅記事のなかで、「丸山千枚田」「奥入瀬渓流」「尾瀬国立公園」などの、新緑が美しい自然豊かな観光地や散策ルートをご紹介します。
キャッシュレス決済を利用する方が増えるなか、最も使用されているのがクレジットカード。しかし、これまでクレジットカードをあまり使用されていなかった方や、これからクレジットカードの使用を考えている方には分からないことも多いのではないでしょうか。そこで今回は、いまさら聞けないクレジットカードの使い方や、注意したいポイントについてご紹介します。
語源・由来|「お雑煮」「羽根つき」 正月にまつわるめでたい由来
季節ごとの習わしや行事食は多々あれど、中でもお正月にまつわるものは、多く現代に残っています。今は簡略化されてしまって、そもそもの由来に思いを馳せることは少なくなっているかもしれません。今回は「お雑煮」と「羽根つき」が始まった理由や、言葉の意味をご紹介します。
イベント事のマナー|年の前半の締めくくり「夏越の祓」で、後半も健やかに
6月の終わりに行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、半年分の穢れを祓って夏を迎え、残りの半年を健やかに過ごすための神事。日本各地の神社で行われ、基本的にどなたでも参列できます。今回は、年の前半の締めくくりである夏越の祓について、また、茅の輪(ちのわ)くぐりのふるまい方についてご紹介します。
散策|美しい渓流や苔に癒やされる川沿い散策「奥入瀬渓流」(青森県)
十和田八幡平国立公園(青森県)を代表する景勝地のひとつが「奥入瀬(おいらせ)渓流」です。十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流は、国指定の特別名勝、天然記念物にも指定されています。四季折々の自然が満喫でき、遊歩道もしっかり整備されています。高村光太郎作の乙女の像でも知られる十和田湖と合わせての散策がおすすめで、ガイド付きのネイチャーツアーも開催されています。「星野リゾート奥入瀬渓流ホテル」で大人で優雅なリゾートも楽しめます。
最新の投稿
コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。
春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。
華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。
日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。
引っ越し時や家電製品の買い替えなど、不用なものが発生した時に困るのが、処分方法ではないでしょうか。不用品の処分は品目によって方法が異なり、業者を利用するなどの方法もあります。そこで今回は、家庭で発生した不用品の処分方法について解説します。


















































